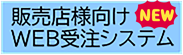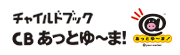お知らせ
☆INTERVIEW☆ “問いかけ”から”子ども主体”が始まる
2026年度のチャイルドブックの見本が完成いたしました。これから来年度のご採用に向けて、先生方にご覧いただけたらと思います。今回はチャイルドブックの総合保育絵本で、監修者としてご協力をいただいているお茶の水女子大学の宮里暁美先生に、総合保育絵本、子ども主体といったテーマでお話を聞きました。宮里先生は、幼稚園教諭、こども園園長などを歴任し、現在お茶の水女子大学アカデミック・プロダクション寄付講座教授に就かれています。

宮里暁美先生
◎“子ども主体”につながる“問いかけ”
●チャイルドブックの総合保育絵本は、「問いかけ」を大切にしていますが、宮里先生は「問いかけ」をどのように捉えていますか?
「問いかけ」は、正解を期待するものではありません。その「問いかけ」によって、子どものなかにわき起こってくるものに価値があると思います。
問いかけをすると子どもたちは考えます。いっぱい考えて、みんな自由にいろいろ言えることがよいのです。正解を言うためではなく、想像を巡らすことが大切です。子どもたちが考える時間を設け、自由に言えることを担保するのが保育者の役割だと考えます。
例えば、キャベツ畑にモンシロチョウがとまっている写真があって、「なにをしているかな?」という「問いかけ」があるとしますね。

「卵を産んでいる」という答えが思い浮かびますが、子どもたちのなかには、もっとたくさんの「なぜ?」や「こうかな?」が生まれます。
「キャベツを食べている?」「鳥から隠れている?」「寝るためじゃない?」。子どもたちのなかに「なぜ?」が広がり「こうだと思う」といういろいろな考えが浮かびます。いわば、「なぜ?」を追う「なぜなぜ博士」になります。

なぜなぜ博士となった子どもたちは、身の回りのさまざまなものに「?」を抱くようになり、それを追求するようになります。ここから「子ども主体」が始まります。
◎“集団への読み聞かせ”と子ども主体
●集団への読み聞かせは、「子ども主体」に沿わないという考え方もあります。
「子ども主体」というのは、全てのことを子どもから始めるということではありません。さまざまなことを経験して、いろいろなおもしろさを知った子どもたちが、自分から「やってみたい!」と言い出す、その時を大切にする、ということなのです。
園での読み聞かせがそのきっかけになることはよくあります。みんなでいっしょに読んでいると、自分が思ってなかったような友達の声も聞こえてきますよね。それに影響されて、自分のなかにも新しい発想が生まれてくるのです。
特に総合保育絵本は「不思議なものを見つけよう」「おもしろいものが周りにいっぱいあるよ」っていう呼びかけになっていますよね。実際、身の回りには未知のものがたくさんあって、子どもたちは日々あらたなものと出会います。そうした出会いのなかから、自分の「なぜなぜ」を探していってほしいですね。それがまさに「子ども主体」ということなのです。

◎一人が一冊ずつ持つ理由
●月刊絵本は、一人が一冊ずつ絵本を持つことになりますが、どのような良さがありますか?
月刊絵本は、みんなが同じものを持っているというところに良さがあります。「絵本で見た虫を見つけて、みんなで盛り上がった」「〇〇くんは、この問いかけに、おもしろい答えをしていた」「先生の読み方が楽しかった」など、園でいっしょに読んだ絵本には、さまざまな記憶が塗り重ねられていきます。
みんなで読んだあと、絵本をロッカーから取り出してきて一人で楽しんでいることもありますし、なん人かの友達と見て楽しむということもあります。家庭に持ち帰ってからも、さまざまなことを思い出しながら読み返すという経験は、一人が一冊の絵本を持っているメリットです。
●家庭に持ち帰った月刊絵本で、園での保育者の話しぶりをまねしたりしながら、保護者や兄弟に読んであげる子もいるようです。
月刊絵本は、園生活のなかでいろいろな思いがこもって、家庭に持ち帰ってからは、その思いが保護者に伝わります。「先生がね…」「〇〇ちゃんがね…」。そこから、保護者の方は園生活の様子を知り、会話が広がっていきます。
月刊絵本には、そうした園と家庭を結ぶ役割もあります。絵本を持ち帰る際、お迎えのときなどに「この絵本でこんな発見をしました」「生き物のコーナー、すごく楽しみました」という一言を添えると、家庭での会話が広がりやすくなりますね。 園でも家庭でも、月刊絵本を存分に活用してほしいですね。